CONTENTS
美加登家(みかどや) について
コンセプト
津和野の “小京都” と称される情緒ある町に佇む、美加登家は元旅館を改装した純和風の一軒家。昭和28年建築の建物は、木組みや欄間など随所に職人の技が残り、どこか時間が止まったような空間が広がります。

料理の柱は、日本一と称される清流・高津川で獲れる 天然鮎。日原から横田にかけて限定仕入れされたものを使用し、その香りと味わいを最大限に引き出すシンプルかつ丁寧な調理が特徴です 。鮎だけで組むコースのほか、季節のすっぽんコースや和牛会席など、四季の素材を大切にした献立構成です。
高津川はダムがなく、全国の一級河川の中で「水質日本一」に複数回選ばれており、その澄んだ流れが育む苔を食む鮎は、香りと旨みが格別です 。

大将(山根一朗 氏)
三代目となる 山根一朗さん は地元津和野出身。地元の高校卒業後、日本各地で修行を積み、25歳で帰郷、美加登家の板前となりました。
2023年には TBS「情熱大陸」に出演し、高津川の鮎を知り尽くした料理人として全国に紹介されました 。自身が地域と鮎への敬意を込めて焼き上げる天然鮎の塩焼きは、シンプルながら食通を唸らせる逸品です。
料理を通じて高津川の自然と町の文化を伝える姿勢は、まさに地域密着型の名店の矜持といえます。
四代目について
京都の名店「緒方」での修業を経て、現在は津和野に戻り、美加登家で腕をふるう四代目。三代目・山根一朗さんのご子息として、すでに現場に立ち始めている。
緒方仕込みの所作や感覚を持ち込みつつも、この土地に根ざした味を大切にしているのが印象的だ。高津川の天然鮎をはじめとする素材への敬意、味の輪郭を削ぎ落とすような仕事ぶりには、若さ以上に“継ぐ者”としての責任と覚悟がにじむ。
厨房では、三代目との呼吸も自然で、互いに言葉少なに手を動かしながら、流れるように一皿一皿が仕上がっていく。あくまで家業として、肩肘張らず、けれども丁寧に受け継いでいく姿勢。その空気感が、料理にもそのまま映っている。
器選びや構成には、緒方で培った感性がほんのりと顔をのぞかせる場面もあるが、それが過度に出ることはない。あくまで美加登家の味として、津和野の時間軸の中にしっかりと溶け込んでいる。
若き四代目が加わった今の美加登家には、代々が積み重ねてきた静かな自信と、これからの余白が同時に感じられる。すでに「継承」と「更新」が始まっているのだと思わされた。
レストランの評価
島根・津和野の小さな町にあって、美加登家の名は料理界のなかでも確かな存在感を放っている。
特に近年は、食べログアワードにおいて連続受賞という実績がその確かさを物語る。2025年にはSilver、2024年はBronze、その前の数年もSilverやBronzeを行き来しながら、安定した評価を維持している。地方にありながら、遠方から通う客の多さにもそれは表れている。
さらに、「日本料理 WEST 百名店」にも度々選出。全国の料理人や食通たちが支持する一軒として、東京や大阪と並んで名を連ねている事実は重い。都市部の名店と同じ土俵で勝負できる力があるということだ。
また、フランス発のレストランガイド「ゴ・エ・ミヨ」では16点/20点と高得点で紹介されており、評価は国内にとどまらない。土地の恵みを芯に据えながらも、研ぎ澄まされた料理構成と器使い、味の余白までを美しくまとめ上げる力量は、こうした外部の評価機関にも確かに届いている。
口コミでは、天然鮎づくしのコースが最も多く語られている。「鮎を焼くだけで、ここまでの表現ができるのか」と驚く声や、「一年に一度は訪れたくなる」「焼き、うるか、鮎飯…最後まで一切ブレがない」といったリピーターの感想も多い。
特に、珍味としてのうるかや、それに合わせる地酒の組み合わせも秀逸との声があり、ただ素材が良いだけでなく、全体の流れの中で味の記憶を引き出す設計力が高く評価されている。
こうした受賞歴や実食レビューを追っていくと、美加登家の魅力は「派手な革新」ではなく、「土地と技の継続」にあることがよく分かる。全国的な賞を受けながらも、過度な脚色や演出は一切なく、ただ静かに、美味を積み重ねている。
その静けさこそが、この店の最大の力なのだと思わされる。

ダイニングプレリュード
外観・エントランス
津和野の町に溶け込むように建つ、美加登家の外観。元旅館を改装したという建物の面影を色濃く残しながら、現在の割烹としての空気をまとっている。
正面の木戸は無垢材のまま、装飾ひとつなくすっと立ち、上部には静かに青い暖簾が一枚掛かるのみ。通りに面してはいるが、その存在を誇示しない佇まいが、この店の姿勢そのものを表しているようにも感じる。
軒先に掲げられた「旅館」の文字が、かつての時間を受け継ぐ名残りとして今も残っており、それがまた、この地に根ざしてきた年月の深さを静かに語っている。

玄関脇の生簀には高津川の天然鮎が泳ぎ、訪れる者に料理の核を先に伝えてくれる。建物全体が「ここでしか味わえない時間」を丁寧に包み込んでいて、足を踏み入れる前からすでに、期待と静けさが同居する。
賑わいではなく、抑えられた空気で惹きつける。その引力に、店の本質が滲んでいた。

ダイニングスペース
建物の外観が静かで控えめであるように、室内もまた、過度な演出のない凛とした空気に包まれている。
通されたのは、畳敷きの個室。引き戸の向こうにひっそりと設けられた床の間には、掛け軸と小さな一輪挿し。わざとらしくない季節のあしらいが、食事の場としての緊張を少しだけ和らげてくれる。

障子越しに差し込む柔らかな光も含めて、空間全体が料理の一部として設計されている印象だ。天井は低め、壁は渋めの緑と白で切り分けられ、椅子席でありながら和室の落ち着きはそのまま残っている。
隣室とは襖で仕切られ、必要に応じて空間の広さも変えられる造り。聞こえてくるのは、器の音と小さな声だけ。賑わいではなく、静けさの中で味わう時間がここでは標準なのだと思わされる。

素材の持つ香りや余韻を邪魔しない、しんとした空間。まるで、料理が語りはじめるのを待っているかのような設えだった。


メニュープレゼンテーション
美加登家では、季節によって内容が大きく変わるおまかせコース一本での提供。7月は、高津川で揚がる天然鮎を主軸に据えた「鮎づくし」の構成となる。
コースは前菜から締めのご飯まで、一貫して鮎を多面的に味わわせる流れ。その日ごとの仕入れによって構成が若干変わるものの、軸となるのは以下のようなラインナップ。
美加登家の年間コース構成
美加登家では、鮎の季節(6月~9月末)とオフシーズン(10月以降から春まで)で、明確に異なるおまかせコースが提供されます。
● 鮎コース(6月~9月末)
高津川産の天然鮎を素材の中心に据えた「鮎づくし」コース。
-
背ごし(生の薄造り)から始まり、「洗い」に変わることも。
-
冬瓜と鮎のお椀、鮎の塩焼き、山椒醤油がけ、うるかや茄子との炊き合わせ、鮎の酢の物、鮎フライなど全10〜11品前後。
-
締めは鮎めし、デザートに青梅の甘露煮のかき氷が出されることもある。
-
値段帯は約11,000円~16,500円(税込)ほどで、仕入れ量や内容によって変動する形式。
● オフシーズンの会席・旬食材コース(10月〜5月末)
鮎禁漁期には季節の食材や地元の幸を活かした会席料理に切り替わります。
-
10月以降は「子持ち鮎生あぶりコース」(約33,000円)、松茸入り子持ち鮎コース(約55,000円)などが登場。
-
冬期〜春先には、天然すっぽんコース(約33,000円)、ふぐコース(養殖16,500円〜/天然33,000円)、花山椒と島根和牛のコース(約33,000円〜)、熊・猪など野生肉と島根和牛の食べ比べコース(約41,800円〜)も展開されている。
-
12月〜翌5月には、スタンダードな会席料理(島根和牛や地元野菜中心)を11,000円~16,500円の価格帯で提供されます。
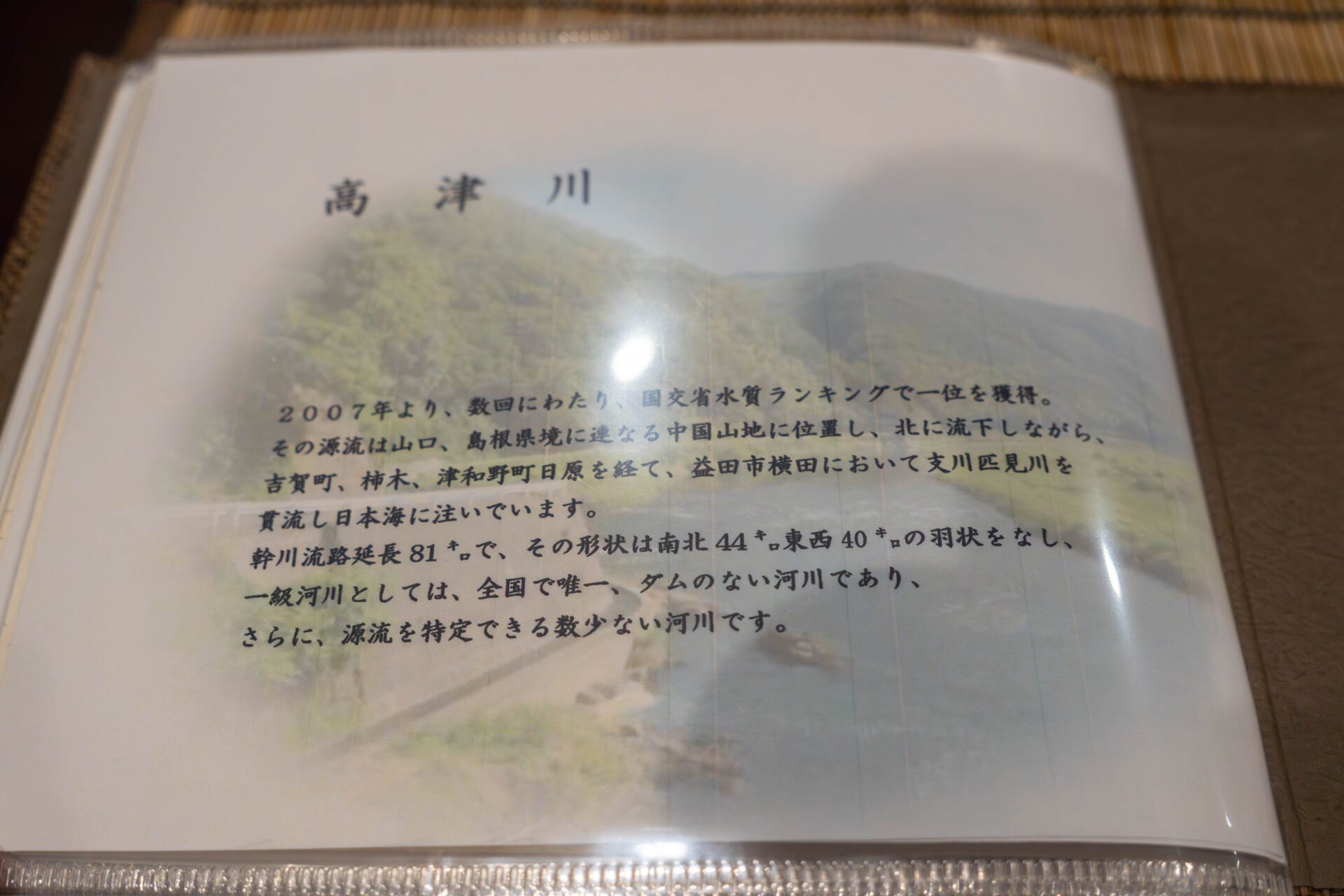
スタータードリンク
この日選んだのは「鮎酒」。温めた酒に炙った鮎が一尾そのまま沈められていて、立ち上がる香ばしさと内臓のほろ苦さが印象に残る。
酒というよりも、ひとつの鮎料理として成り立っているような一杯。料理との流れにも無理がなく、自然に馴染んでいた。


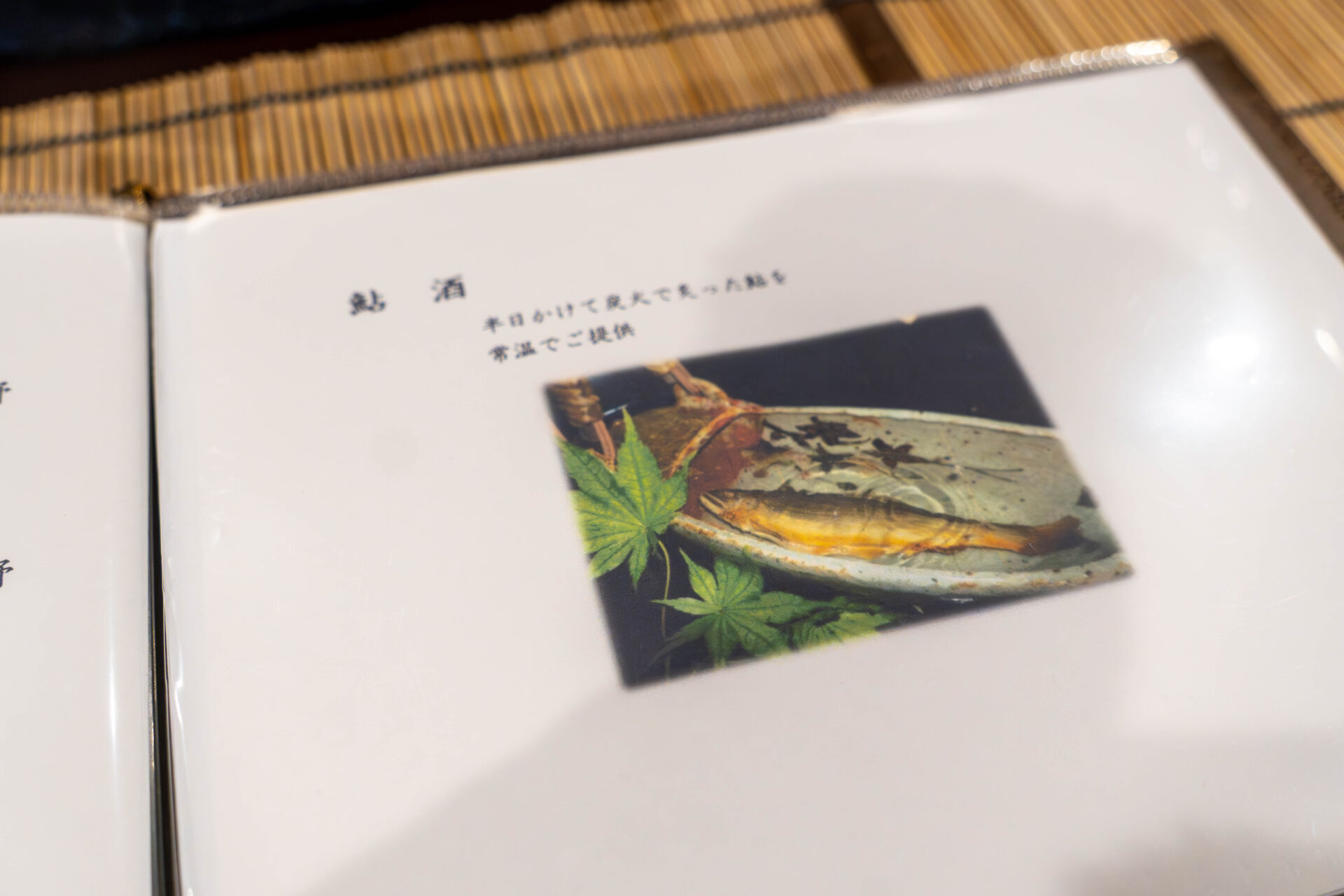
実際に味わった料理
鮎の南蛮粥
南蛮漬けにした鮎をからりと揚げ、粥状のとろみある餡にあわせた一皿。粥といっても米粒は感じず、なめらかに仕立てられた餡が、酸味とともに揚げた鮎をやさしく包み込んでいる。
骨はほどよく残っていて、揚げの香ばしさとともに鮎の身の締まりも感じられる。噛むほどに旨みがにじみ出る、端正な仕事。粥のほのかな甘みと酸味がバランスを取り、ひと口ごとに口の中でまとまっていく。
ガラスの皿に盛られた透明感のあるビジュアルも涼やかで、夏の鮎を静かに立ち上げるような構成だった。

鮎と冬瓜のお椀
焼いた鮎の半身と、やわらかく炊いた冬瓜をあわせたお椀。澄んだ出汁の中にほんのりと焼きの香りが移り、蓋を開けた瞬間に広がる香気が印象的だった。
焼き目を残した鮎は、皮の香ばしさと身のしっとり感のバランスがよく、出汁を吸った冬瓜との相性も穏やか。主張しすぎないが、どちらも確かな存在感を残していて、素材同士の調和がとれている。
器は銀色の金属製で、ややモダンな質感ながら、温度をしっかりと閉じ込めていて、開けた瞬間の熱と香りがしっかりと立ち上がる設計。鮎の香りを「閉じ込めて届ける」ための器として、理にかなった選択に感じられた。
コースの中盤に置かれることで、香りと温度、そして一度落ち着くための余白が生まれていた。

鮎の背ごし
氷を敷き詰めた器の底に、そっと潜ませるように盛られた鮎の背ごし。ひと切れずつ氷の中から取り出し、紙で水気を切っていただく。
生のまま、骨ごと薄く引かれた鮎は、口当たりが驚くほどなめらかで、香りは澄んでいる。
背ごしという形でこの料理が成立するのは、もとより高津川の鮎だからこそ。
生で食べられる清らかさと、それを骨ごと引けるだけの確かな包丁仕事が揃って、はじめて一皿として成り立っている。
静かな一品だが、素材の力と技術の確かさがごく自然なかたちで伝わってくる。




鮎の姿焼き
焼きで登場した鮎は、やや小ぶりなサイズ。脂ののりよりも香りが際立つ時期の個体で、皮目の香ばしさと身の引き締まりが印象的だった。
焼きは強すぎず、皮はパリッと、身はほどよくふっくら。サイズを活かした焼き上がりで、香りの立ち方が特に心地よい。
添えられた蓼酢は、ごく控えめな酸味と青みがあり、鮎の風味を邪魔せずすっと引き立てる。全体として塩と火入れだけで完成されたところに、わずかに加えるこの酸味が、口をもう一度整えるような役割を果たしていた。
小ぶりな鮎ならではの香りの抜け方が楽しめる、一本目にふさわしい姿焼きだった。


鮎の春巻き
供されたのは、紙を巻いた状態で仲居さんの手から直接手渡しされる一本。受け取った瞬間に分かるほどの熱さで、まずその温度に少し驚く。皮は香ばしくパリッと揚がり、かぶりつくと中から立ちのぼる鮎とうるか味噌の香りが一気に広がる。
中身はほぐした鮎の身に、うるか味噌がほんのりと。コクはあるが重すぎず、春巻きの軽さを損なわないバランス。そのまま食べ進めていくと、下の方から香り高い実山椒が顔を出し、口の中が一度リセットされるような余韻が残る。
味の変化がしっかり設計されていて、一口の中に流れがある。さらに最後まで温度が落ちないのも印象的で、火入れと包み方の精度の高さがうかがえる。
つなぎではなく、コースの中でしっかりと役割を持った一品。素材・構成・技術、それぞれがきちんと噛み合っていた。


焼き鮎(二本目)
続いて出てきたのは、一本目よりやや大ぶりの鮎。身の厚さが増す分、香ばしさだけでなく、鮎そのものの風味や質感がよりくっきりと感じられる。
焼きの具合は変わらず丁寧で、皮目はパリッと香ばしく、中はしっとり。ほろ苦さや内臓の旨みも引き立っていて、素材の成熟度合いがそのまま味に表れている。
鮎という魚の輪郭が、一層はっきりと伝わる一本だった。サイズの違いが意図として明確に読み取れる構成で、単なる重ねではなく変化としての連なりになっていた。



子うるか
追加でお願いしたのは「子うるか」。高津川で秋の終わりに獲れた鮎の卵を、白卵の状態で塩漬けにし、そのまま熟成・発酵させたもの。
いわゆる珍味の中でも、比較的すっきりとした口当たりで、塩気や旨みはしっかりあるものの、クセは強くない。酒がなくてもそのまま味わいやすいというのも頷ける。
きらきらと冷えたガラスの器に収められ、季節外れの鮎が、保存の技術と時間の流れの中で、また別の命を宿したようなひと品だった。

炊き合わせ:うるか茄子
締めのごはんに添えられたのは、うるかで炊いた茄子。鮎の内臓を塩漬けして発酵させたうるかは、濃厚な旨みとほのかな苦みを持ち、茄子のやわらかな果肉に深く染み込んでいる。
煮汁には余分な味がなく、発酵による旨みが穏やかに立ち上がる。その残り汁に白米を落として口に運べば、米の甘みと発酵のコクがゆるやかに溶け合い、最後のひと口まで満たされる。
鮎そのものだけでなく、鮎を素材として活かす。そうした多角的な“鮎の味わい方”がコースの随所に差し込まれ、構成としても実に印象的だった。





口直し:鮎の酢のもの
焼きものや揚げものを経た後に供される、涼やかな酢のもの。
酢締めにした鮎は、しっとりとした口当たりとともに、身の奥に潜む甘さが引き出されていて、柔らかな酸味の酢と重なることで静かに調和する。
添えられた胡瓜の食感と山芋の清涼感も、全体に瑞々しさを与えていて、鮎という素材の新たな一面を見せてくれる。
口をリセットするだけでなく、これまでの流れを整理し、次へと続く余白をつくるような一皿。


鮎ご飯と白味噌仕立ての汁物
締めのご飯は、香ばしく焼かれた鮎の身をふんだんに混ぜ込んだ鮎ご飯。
しっとりとした身と、皮の香ばしさが米粒に染み込み、噛むほどに鮎の風味が広がる。塩加減は控えめで、最後まで食べ飽きない絶妙なバランス。
合わせて供される白味噌仕立ての汁は、ふわりとした甘みとまろやかさがあり、食後の余韻をやさしく整えてくれる。
一連のコースを締めくくるにふさわしい、落ち着いた構成。最後まで素材を尊重した流れが貫かれている。


青梅の甘露煮
デザートは、青梅の甘露煮を忍ばせたかき氷。
氷の下に隠れていたのは、ふっくらと煮含められた青梅。
芯まで甘みが入りつつも、梅の酸味と香りがきちんと残されていて、後口は爽やか。
濃密な梅の味わいと氷の涼やかさが合わさり、夏の終わりを感じさせる締めくくりにぴったりだった。


まとめと感想
津和野の町を流れる高津川。
その澄んだ水で育った天然の鮎を、三代にわたって受け継いできた料理人の手で味わう――
これは単なる食事ではなく、“風景を食べる”ような体験だった。
山々に囲まれ、川音の届く静かな地で、自然とともに生きる人々の営みが一皿ごとに立ち上がる。
鮎の身をほどくと、その中に流れていた時間や川の匂いまで思い浮かぶ。
それは、高津川という稀有な川の力だけでなく、代々この地で鮎と向き合い続けてきた家族の積み重ねがあってこそ。
今の主人である三代目の手から伝わるのは、ただ技術や知識だけではない。
この土地で鮎を扱うことへの覚悟と敬意、そしてその先にある「今、ここでしか食べられないもの」を届けようとする意志だった。
器に盛られているのは「料理」だけではない。
津和野という土地が持つ静けさや、美しさ、慎み深い誇り――
そうした空気までもが、ひと口ごとにじんわりと染み込んでくる。
丁寧で控えめなおもてなしもまた、この場所の魅力のひとつ。
説明しすぎず、押し付けず、でも常に目配りがあり、食べる側に委ねる距離感が心地よい。
都市では決して再現できない、原風景に触れるような時間だった。
季節の手触りと土地の記憶が、料理というかたちを借りて静かに語られていく。
そこに、ほんとうの“贅沢”があると感じさせられた。

予約とアクセス情報
予約方法
-
完全予約制で、電話予約(2名様以上)のみ受付可能です。1名での予約はできません。
ご希望日の予約は早めに電話でご確認いただくのが確実です。 -
「ポケットコンシェルジュ」や一部予約サイトで受付される場合がありますが、電話予約が確実です。
営業時間・定休日
-
営業時間(いずれも最終入店時間)
• ランチ:12:00~13:00
• ディナー:17:00~19:00 -
別情報として11:30スタートの表記もありつつ、表記の相違があるため、電話確認が安心です。
-
定休日:毎週月曜日および8月14日〜16日が夏季休業
アクセス・所在地
-
住所:島根県鹿足郡津和野町日原221‑2
-
最寄り交通:
• JR山口線 日原駅より徒歩15〜21分、またはタクシーで約3〜5分
• 萩・石見空港から車で約25〜30分 -
駐車場:あり(6台)
おすすめの時期
-
鮎コースの提供時期:芳醇な旬の鮎を味わえるのは、6月〜10月末頃の期間です。特に夏の高津川の鮎にこだわりたい方には、この時期がおすすめ。
-
津和野の観光に最適な季節:10月〜11月は、津和野城跡から「雲海(雲海現象)」を見られる可能性のある時間帯があり、風情ある景色と合わせて訪れるには特におすすめです。
-
- TAGS


