CONTENTS
お料理ひろ岡 について
コンセプト
近鉄奈良駅からほど近く。静かな通り沿いに佇む「お料理ひろ岡」は、落ち着いた雰囲気の中で、季節の料理をゆっくり楽しめるお店です。
食材の良さを引き出す丁寧な仕事をベースに、ときには香りや食感を重ねるようなひと工夫も。
全体としてはやさしく穏やかな流れの中に、ところどころ小さな驚きや遊び心も感じられました。
移転前のことは知らずに伺いましたが、街中にこういう食事を楽しめる場所があることが素直に嬉しくなるような、そんな一軒です。
廣岡大将について
店主の廣岡大将は奈良・五條のご出身。
実家の居酒屋で料理に触れたことが、料理の道へ進むきっかけに。
自分の感覚を頼りに、少しずつ積み重ねてきた経験が、今の料理の中にも自然と息づいています。
気取らず、無理をしない。けれど、どの皿にもきちんと向き合っている。
そんな料理の姿勢から、大将の人柄やこれまでの歩みが、静かに伝わってくるようでした。
五條時代にはミシュラン一つ星を獲得し、今は奈良の街中で、また新たに日々の料理と向き合っています。

レストランの評価
「お料理ひろ岡」は、奈良・五條に店を構えていた当時から注目され、
2022年版のミシュランガイド関西では一つ星を獲得。
現在の奈良駅近くへの移転後も、その評価は引き続き保たれています。
料理の派手さで勝負するのではなく、日々の積み重ねや丁寧な仕事が食べ手に伝わっているからこその評価。
口コミなどでも「落ち着いて食事ができる」「料理にブレがない」といった声が多く、
観光客だけでなく、地元の方々からの信頼も厚いようです。
知る人ぞ知る、という雰囲気を残しながら、確かな実力と信頼を持った一軒です。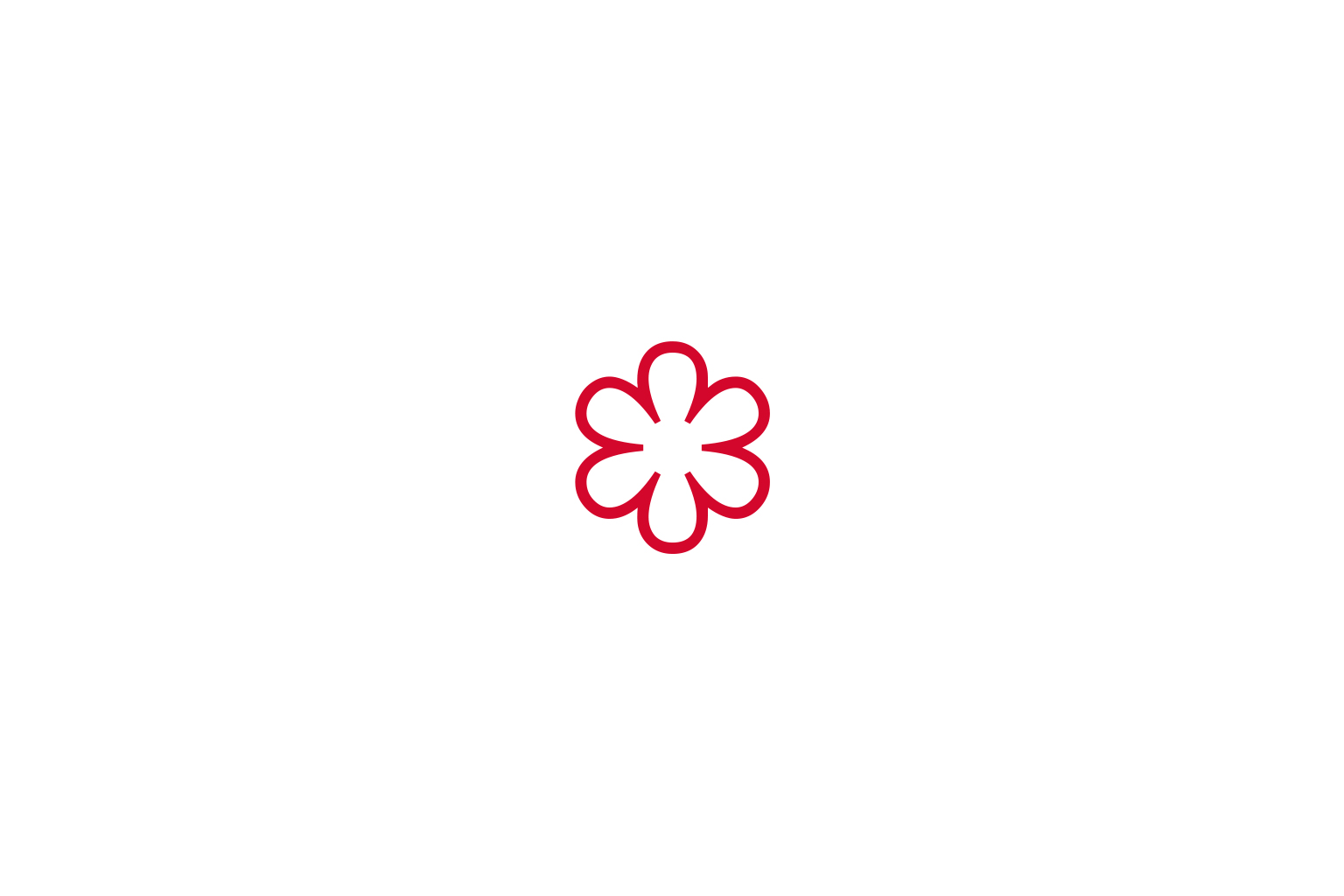
ダイニングプレリュード
外観・エントランス
近鉄奈良駅から歩いてすぐ。商業施設やホテルが立ち並ぶ通り沿いに、控えめに佇む「お料理ひろ岡」。
看板も目立ちすぎず、通り過ぎてしまいそうになるほどのさりげなさがありますが、そこがまた、この店らしさでもあります。
扉を開けると、外の喧騒がすっと遠のくような静けさ。
木の質感を生かしたエントランスや小さな飾りに、大将の美意識がにじんでいて、必要以上に飾り立てない落ち着いた空気に自然と気持ちが整います。
“特別な空間”というより、“余計なものがない空間”。
初めて訪れても構えることなく、ゆったりとした気持ちで足を踏み入れられる入り口です。


ダイニングスペース
店内は、静謐で無駄のない空間構成。
木の温もりと柔らかな間接照明が落ち着いた時間をつくり、
床の間の花器や設えの一つひとつにも、大将の美意識が細やかに息づいています。
特徴的なのは、大将の隣にお客さんが座るカウンターの配置。
厨房とのあいだに一切の境がなく、料理人の所作や息づかいを間近に感じられる設計で、
大将自身も「日本一、お客さんと距離が近いお店かもしれません」と笑っていました。
その自然な距離感が、料理の説明や空気そのものを和やかにしてくれます。


メニュープレゼンテーション
席に着くと、メニュー表などはなく、特にあらたまった説明もありません。
「おまかせで進んでいく」ということが、自然と伝わってくる静かな始まり方。
季節に合わせて組まれたコースが、大将の手から淡々と、けれど丁寧に供されていく。
その流れに、こちらも言葉ではなく、自然と身をゆだねるような感覚があります。
決め込まず、説明しすぎず、けれど流れに迷いがない。
そんな静かな導入から、この店の料理に対する姿勢がそっと立ち上がってくるようでした。
スタータードリンク
食事の始まりは、お酒から。
いきなり大将おすすめの日本酒という選択肢も魅力的でしたが、
この日はまず、サッポロ黒ラベルの小瓶をお願いしてスタート。
冷えすぎず、適温で供される瓶ビールをゆっくりと口に含むと、
少し張っていた気持ちがすっとほどけていくような感覚に。
これから始まる食事に向けて、静かに整えてくれる一本でした。

実際に味わった料理
噴火湾の毛蟹と長崎・茂木の枇杷
コースの幕開けは、今が一年でいちばんおいしいという、北海道・噴火湾の毛蟹。
しっかりと身が入り、甘味も旨味も濃い立派な蟹に、合わせられたのは長崎・茂木の新物の枇杷。
淡くみずみずしい甘さが、毛蟹の濃厚さを引き立て、どちらも主張しすぎず、すっと馴染んでいました。
上からかけられたのは、とろみのあるやさしい出汁。
旨味をやわらかく包み込み、ひと口目からすっと季節の世界へと引き込まれるような一品でした。
器には端午の節句にちなみ、刀を意味する菖蒲の葉をあしらって。
味覚だけでなく、しつらえの細やかさにも心がほどけるような、穏やかなスタートでした。

お凌ぎ:銀しゃりと白海老、熟成カラスミ
続いてのお凌ぎは、大将の地元・奈良県五條市のヒノヒカリを使った銀しゃり。
土鍋でふっくらと炊かれた米の香りに、自然と背筋が伸びるような、静かな一皿。
その上に重ねられるのは、富山湾にしか生息しない旬の白海老。
とろりとした甘さと繊細な食感が、温かなご飯にふわりと溶け込んでいきます。
さらに、大将が2年以上かけて熟成させた自家製のカラスミを、少しだけお酒で戻してひと匙。
上にはキャビアをのせて、塩気と旨味の重なりに奥行きを持たせています。
主張しすぎない銀しゃりを土台に、海の恵みと手間の重なりが少しずつ浮かび上がってくるような、控えめながらも印象深いお凌ぎでした。


お椀:うすいえんどうの出汁と炭火焼き白甘鯛
春の香りをまとったお椀。
五條産の朝採れうすいえんどう豆をなめらかに裏ごしした出汁は、やさしい甘みと淡い緑色が印象的で、器に顔を近づけるとほっと気持ちがほどけます。
中央には、徳島・宍喰の白甘鯛を炭火で香ばしく焼いたもの。
表面はパリッと香ばしく、中はふっくらとやわらかく、豆の甘みと炭の香りが自然に溶け合っていきます。
その甘鯛の下には、ふるふるとした玉子豆腐がそっと仕込まれており、
すべてが一体となって、ひと口ごとに穏やかな余韻が広がる、春の景色を思わせるような一椀でした。

お造り①:明石のアイナメ しゃぶしゃぶ仕立て
お造りのひと皿目は、明石で水揚げされたアイナメ。
神経締めされた鮮度の高い身を、熱した油で軽く火入れし、しゃぶしゃぶのような仕立てに。
表面はごくわずかに熱が入り、中心は透明感を残す絶妙な火通し。
身の繊細な旨味ととろりとした舌触りが口の中でふわりとほどけていきます。
添えられているのは、梅を忍ばせた大根おろしと山葵。
酸味と辛味がやさしく重なり、油のまろやかさをすっと引き締めてくれる組み合わせでした。
青白い染付の器にのせられた、静かな存在感のある一品。
香り、温度、味の移ろいがきちんと計算されている、丁寧な一皿でした。

長崎・壱岐の地で焼酎と日本酒の両方を手がける重家酒造が造る、夏季限定の一本「よこやま 夏純吟」。


お造り②:瀬付き鯵と金胡麻
続いてのお造りは、山口・周防大島の瀬付きの鯵。
よく肥え、脂がしっかりとのった状態で、包丁の入り方も美しく、口に含んだときのとろけ方に品があります。
そこに合わせたのは、五條で唯一の生産者さんが手がける希少な金胡麻。
鯵の表面を覆うようにたっぷりと振られ、香ばしさが口いっぱいに広がっていきます。
上には細かく刻んだ薬味野菜がふんわりと重ねられ、胡麻と鯵の脂をほどよくまとめてくれる存在。
ひと口の中で、香り・食感・旨味が調和する、満足感のあるひと皿でした。
どこか和え物のような趣もあり、料理としての幅の広さも感じさせてくれるお造りです。

揚げ物①:そら豆と野付半島の帆立
揚げ物のひと皿目は、シンプルながら印象に残る組み合わせ。
使われているのは、朝採れの五條産そら豆と、北海道・野付半島の天然帆立の貝柱。
帆立は、干しすぎない一夜干しのような手当を2日かけて施したもの。
水分が適度に抜け、旨味がぐっと凝縮されています。
そら豆のほくっとした食感と、帆立のねっとりした甘味が衣の中で自然に寄り添い、
噛むごとにそれぞれの香りがふわりと立ちのぼります。
味付けは塩のみ。余計なものを足さず、素材の輪郭がはっきりと感じられる、静かで力のある一品でした。

揚げ物②:対馬の穴子 青柚子の香り
二品目の揚げ物は、長崎・対馬の肉厚な穴子を使った一皿。
しっかりと煮て、ふわふわとろとろに仕立てた穴子を、さらに衣をまとわせて天ぷらに。
噛んだ瞬間に外はさくっと、中からはじゅわっと旨味が広がり、
煮穴子ならではの柔らかさと、揚げの香ばしさが同時に味わえる贅沢な仕立てです。
仕上げには、青柚子の皮をたっぷりと削りかけて。
揚げ物特有の重たさを感じさせない、爽やかで印象的な余韻を残してくれます。
素材の持ち味と丁寧な下ごしらえ、香りの一手が重なり合った、記憶に残る一品でした。

焼き物:久美浜の鳥貝 肝醤油と山椒香
焼き台に備長炭の熱が静かに広がる中、大将の手でじっくりと焼かれていくのは、京都・丹後 久美浜の肉厚な鳥貝。
目の前で焼かれることで、香りや温度の変化まで含めて五感で楽しめる時間です。
火入れに使われているのは、奈良・辻村さんによる陶器の火鉢。
そこに山椒の香りを移したオイルを塗りながら焼くことで、香りがふわりと立ちのぼり、鳥貝の甘味を引き立てます。

仕上げには、鳥貝の肝を使った自家製の肝醤油をさっとひと塗り。
香ばしさ、ほのかな苦味、旨味のすべてが重なり、シンプルながら一切の無駄がない構成。
串に打たれたその佇まいも含めて、記憶に残る焼き物のひと皿でした。


口直し:三輪そうめん 白髪 新生姜出汁と焼き茄子
メインの余韻を引き継ぎながら、静かに気持ちを整えてくれる口直し。
供されたのは、奈良・三輪山本の3年熟成「白髪」という極細のそうめん。
その名の通り、ほとんど白髪のように繊細な糸のような麺が、上品な出汁にふんわりと泳ぎます。
出汁は新生姜をきかせたやさしい味わいで、食べ進めるごとに体の内側からじんわりと温まるような感覚。
中には相性のよい焼き茄子がしっとりと沈み、さらに秋田・じゅんさいがさりげなく添えられていました。
冷たさや強さではなく、やわらかさで口を整えるという一杯。
静かな余白が、また次の皿への準備をしてくれます。

山三(やまさん)純米大吟醸 愛山45磨き 無濾過生原酒
奈良県・美吉野醸造さんによる一本。
愛山を45%まで磨き上げ、無濾過・生原酒ならではのふくよかさと、キレのある飲み口が印象的な食中酒です。

白味噌仕立て:花山椒と生さえずり
椀の中で、白味噌のまろやかな出汁に、五條産の花山椒がふわりと浮かぶ春らしい一品。
その香りに誘われるように、自然と手が伸びる。
中には、生のミンククジラのさえずり。
臭みは一切なく、特有の味わいとしなやかな弾力があり、
ひと口ごとに白味噌の旨味と花山椒の香りが溶け合っていきます。
ポイントは、花山椒をしっかりと絡めながら口に運ぶこと。
ふくよかな味わいの中に、ピリッとした香りが立ち上がり、輪郭が生まれます。
さらに、ホワイトアスパラガスの甘みや、天然のせりの野趣も程よいアクセントに。
重たさを感じさせず、静かに余韻を残してくれる、春の終わりにちょうどいいひと椀でした。


銀シャリと釜揚げしらす(〆のご飯)
通常は季節の食材を使った炊き込みご飯を出しているひろ岡ですが、
5月だけは特別に、炊きたての銀シャリが供されます。
米は、大将の地元・五條産のヒノヒカリ。
土鍋でふっくらと炊き上げられ、粒立ちの美しさとほのかな甘みが際立ちます。


合わせるのは、和歌山・増富商店の釜揚げしらす。
門外不出の漁法で水揚げされたしらすは、ふわっとやわらかく、潮の香りもやさしい。
大将が「宇宙一の磯間のしらす」と称するのも納得の味わいです。



まずは、花山椒の佃煮を添えて。
清涼感ある香りがしらすの旨味を引き立て、シンプルながら余韻深いひと椀に。

2膳目では、竹村養鶏場「九極卵」の卵黄ソースを。
とろりと濃厚で、甘さとコク、そして黄身の旨味がしらすと米にしっかりと絡み、思わず笑みがこぼれるおいしさ。
実は、この卵は先のお椀にそっと仕込まれていた玉子豆腐にも使われていたもの。
料理全体の中に、素材が静かに響き合っていたことに気づき、改めて心を動かされる場面でした。




デザート & フィナーレ
甘味①:クインシーメロンと白ワインゼリー
食後の甘味として最初に供されたのは、見た目にも涼やかな一皿。
熊本県産のクインシーメロンをくり抜いた果肉を、白ワインベースのゼリーで包み込んで。
ゼリーにはカルダモンとクローブを忍ばせ、
香りに奥行きを持たせつつも、メロンの甘さはしっかりと引き立つ設計。
上には、紅白の愛らしいポップスター(ダイアンサス)がひとひら。
見た目にも涼やかで、季節の移ろいをやさしく映し出すようなひと品でした。

甘味②:黒川本家の葛餅とれんげ蜂蜜のクリーム
二皿目は、吉野・黒川本家の練りたて葛餅を使ったひと品。
艶やかな透明感とほどよい弾力があり、口に入れるとすっととけるような柔らかさ。
上には、五條で営まれている養蜂場のれんげ蜂蜜入りの生クリームがふんわりと。
この蜂蜜は、二年に一度しか収穫されない、れんげ100%の希少な蜜。
素材の甘みをそのまま引き出すように練り込まれており、くどさのないやさしい後口に仕上がっています。
和の香りと、ミルキーなコクがそっと寄り添うような、
心までほどけるような締めの甘味でした。

まとめと感想
素材の組み合わせに驚きがありながら、どれも無理なくすっと身体に染み込んでいくような構成。
伝統や技巧に頼ることなく、自身の記憶や感覚から自然と立ち上がる“食べたいかたち”が、静かに形になっていました。
その根底には、奈良・五條という土地への深い愛着がある。
朝採れのうすいえんどう、花山椒、ヒノヒカリといった地元の恵みが、料理の随所に散りばめられています。
料理の世界に入ったのも、居酒屋を営む実家での原体験から。
その後、独学で日本料理を学び、今ではミシュラン一つ星として認められるまでに。
誰かの型にはまらず、自分の感覚でここまで辿り着いたという歩みが、どこか料理の佇まいにもにじみます。
また、空間づくりや所作のひとつひとつにも、丁寧で繊細な美意識が宿っていて、
料理だけでなく、時間そのものを味わっているような心地よさがありました。
ひと皿ごとに伝わる手仕事と、素直なセンス。
地元の記憶を、今の自分の表現で届けようとする姿勢。
また違う季節に、大将が“その時いちばん食べてほしいかたち”を見に来たくなる、そんな一軒です。

予約とアクセス情報
予約方法
-
電話予約:0742‑95‑5587
-
ネット予約:TableCheck のフォームまたは公式Instagramプロフィールから可能
-
完全予約制:昼夜ともに前日までの予約が必要です
アクセス
-
住所:奈良県奈良市元林院町15
-
最寄駅:
• 近鉄奈良駅から徒歩約5分(約400 m)
• JR奈良駅から徒歩14分程度(約1.1 km)
営業時間・定休日
-
昼の部:12:00 〜 15:00(ラストオーダー)
-
夜の部:18:30 〜 21:00(ラストオーダー)
-
定休日:毎週水曜&木曜昼の部、毎月1日の昼の部
※営業時間は“一斉スタート制”です。遅れる場合は事前に連絡をお願いします
このレストランを訪れた旅の様子は、Destination: NARA Vol.2 歴史の余韻と静謐に包まれる、奈良美食旅で紹介しています。
- TAGS



